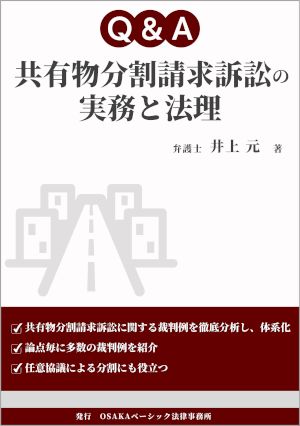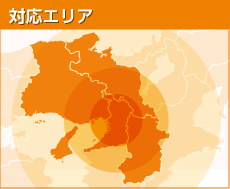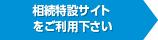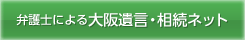共有物分割のトラブル
共有となるケース
不動産が共有となっているケースとして次のような場合が多いようです。
- 先代から共有となっており、これを相続により承継した。
- 親から相続した際、分割方法がまとまらなかったため、とりあえず、兄弟姉妹の共有とした。
- 夫婦共有で自宅を購入したものの、離婚し、未だ、共有状態が解消されない。
共有状態による不利益
しかし、共有状態の場合、次のような不利益があります。
- 共有の場合、単独所有と比べて物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれやすい。
- 共有者間に対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に支障をきたし、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となる。
解決のため共有物の分割を請求することができる
共有には上記のような問題があるため、共有物を分割するよう請求することができます。この権利を共有物分割請求権と言います。
この権利は強力なものであり、最高裁判例では、共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめる権利であるとされています。
具体的には、協議もしくは裁判で次のような方法で分割することになります。
- 現物分割
- 全面的価格賠償による分割(お金を支払って買い取る)
- 換価分割(任意売却もしくは競売)
どのように分割するのかについては、①共有物の性質・形状、②共有関係の発生原因、③共有者の数及び持分の割合、④共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、⑤分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無などを考慮し、協議して決めることになります。
共有物分割のための手続としては、①協議による分割(協議分割)と②裁判による分割(裁判分割)がありますが、先ず、協議を行う必要があります(民法258条1項)。これは、共有物を分割するには細かな利害の調整が必要ですから、共有者間で話し合って、納得する方法で分割することが望ましいからと考えられます。
協議により分割ができないとき、裁判により分割されることになります(裁判分割)。
分割についての留意点
共有は、親族間などの濃密な人間関係を前提とすることが多いように見受けられます。そして、この人間関係が希薄になったり、あるいは完全に破壊されたため、円満な共有関係を維持することができなくなったことから、共有関係の解消が求められます。
しかし、もともと、利用方法や共有関係解消後の権利関係について合理的な取り決めがなされていないため、人間関係の解消に伴って顕在化する共有物分割に際して、合理的な解決が困難であり、トラブルが多発するのではなかと思います。
人間関係を回復することは困難かもしれませんが、分割に際しては、各共有者の利益を合理的に調整することが肝要であると思われます。
人間関係がこじれてしまい、話し合いは困難であっても、共有物分割訴訟を提起すれば、裁判所は、広範な裁量権に基づいて、相応の分割をしてくれるものと期待できます。判決に至ることなく、和解により解決するも多く、迷っているよりも、一歩、踏み出してみることが早期の解決につながるのではないでしょうか?
共有物分割Q&A
- Q01 どのような分割方法があるのか教えてください
- Q02 一部の者の共有を残すこともできるのでしょうか?
- Q03 分割しない約束をすることもできるのですか?
- Q04 どうすれば協議がされたと認められるのですか?
- Q05 任意売却すると決めたにもかかわらず相手方が売却に応じてくれません
- Q06 現物分割はどのようにして行われるのですか?
- Q07 どのような場合に現物分割ができないのでしょうか?
- Q08 現物分割に際してどのような事情が考慮されるのですか?
- Q09 全面的価格賠償はどのような場合に認められるのですか?
- Q10 競売分割とはどのようなものなのですか?
- Q11 相続により共有となった場合の分割の手続を教えてください
- Q12 夫婦もしくは離婚した元夫婦間における共有物分割請求の注意点
- Q13 共有物分割に際してローン(担保権)はどのように処理されるのでしょうか?
- Q14 共有物分割請求が権利濫用とされることもあるのでしょうか?
- Q15 共有物を分割した際に課される税金について教えてください
「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」出版のご案内
弁護士井上元がAmazonで「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」を出版しました。この本は、共有物分割請求訴訟についての多数の裁判例を整理、分析して体系化したものです。豊富な実例を紹介しQ&Aにより分かりやすく解説しています。
※法律専門家の方を対象としています。
ご希望の方は、Amazonのサイトからお買い求めください。
費用
1 相談料
初回無料
2回目以降は30分当たり5,000円(税別)
2 訴訟
| 着手金 | 40万円(税別) |
|---|---|
| 報酬 | 持分額の6%(税別) |
※複雑又は特殊な事情がある場合は別途見積
※実費別途
共有のトラブルでお困りの方は、一度、当事務所にご相談ください。