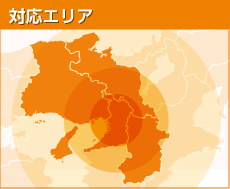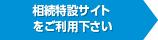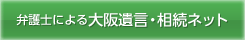サブリース契約と賃料減額請求
サブリース契約とは、一般には、マンション、アパート、オフィスビルなどの建物の所有者が不動産業者(サブリース業者)に建物の全部または大部分を貸す契約で、建物を借りた業者が自らそれを使用するのではなくテナントに転貸するものを指しています。
土地所有者としては、不動産業者の専門的知識や経験を利用して建物を建築し、業者から安定して賃料の支払いを受けて、建物建築費用のための借金を返済し、且つ、収益を上げることが見込めるというメリットがあります。
一方、不動産業者としては、転貸したテナントから土地(建物)所有者に支払う賃料よりも高額の賃料を得て、収益を上げることが見込めるというメリットがあります。更に、建築業者も兼ねている場合には建築請負代金や、管理業も行う場合には管理受託料も取得できることになります。
このようなサブリース契約はバブル時によく利用されましたが、バブル崩壊によりサブリース業者がテナントから受ける賃料が、土地(建物)所有者に支払う賃料よりも低額になるという逆ザヤ現象が生じるようになったことから問題が生じることとなりました。
具体的には、サブリース業者から土地(建物)所有者に対し、借地借家法32条に基づき賃料の減額請求が行われるようになったのです。
最高裁平成15年10月21日判決(平成12年(受)第573号・民集57巻9号1213頁)
このようなサブリース業者の土地(建物)所有者に対する賃料減額請求については、「不動産賃貸権あるいは経営権を委譲して共同事業を営む無名契約である」、「ビルの所有権及び不動産管理のノウハウを基礎として共同事業を営む旨を約する無名契約と解すべきである」などとして借地借家法32条による賃料減額請求を否定する見解と、同条の適用を肯定する見解がありましたが、上記最高裁判例は、次のように述べて、借地借家法32条による賃料減額請求を認めました。
「前記確定事実によれば、本件契約における合意の内容は、第1審原告が第1審被告に対して本件賃貸部分を使用収益させ、第1審被告が第1審原告に対してその対価として賃料を支払うというものであり、本件契約は、建物の賃貸借契約であることが明らかであるから、本件契約には、借地借家法が適用され、同法32条の規定も適用されるものというべきである。
本件契約には本件賃料自動増額特約が存するが、借地借家法32条1項の規定は、強行法規であって、本件賃料自動増額特約によってもその適用を排除することができないものであるから(最高裁昭和28年(オ)第861号同31年5月15日第三小法廷判決・民集10巻5号496頁、最高裁昭和54年(オ)第593号同56年4月20日第二小法廷判決・民集35巻3号656頁参照)、本件契約の当事者は、本件賃料自動増額特約が存するとしても、そのことにより直ちに上記規定に基づく賃料増減額請求権の行使が妨げられるものではない。
なお、前記の事実関係によれば、本件契約は、不動産賃貸等を目的とする会社である第1審被告が、第1審原告の建築した建物で転貸事業を行うために締結したものであり、あらかじめ、第1審被告と第1審原告との間において賃貸期間、当初賃料及び賃料の改定等についての協議を調え、第1審原告が、その協議の結果を前提とした収支予測の下に、建築資金として第1審被告から約50億円の敷金の預託を受けるとともに、金融機関から約180億円の融資を受けて、第1審原告の所有する土地上に本件建物を建築することを内容とするものであり、いわゆるサブリース契約と称されるものの一つであると認められる。そして、本件契約は、第1審被告の転貸事業の一部を構成するものであり、本件契約における賃料額及び本件賃料自動増額特約等に係る約定は、第1審原告が第1審被告の転貸事業のために多額の資本を投下する前提となったものであって、本件契約における重要な要素であったということができる。これらの事情は、本件契約の当事者が、前記の当初賃料額を決定する際の重要な要素となった事情であるから、衡平の見地に照らし、借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求の当否(同項所定の賃料増減額請求権行使の要件充足の有無)及び相当賃料額を判断する場合に、重要な事情として十分に考慮されるべきである。
以上により、第1審被告は、借地借家法32条1項の規定により、本件賃貸部分の賃料の減額を求めることができる。そして、上記のとおり、この減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、本件契約において賃料額が決定されるに至った経緯や賃料自動増額特約が付されるに至った事情、とりわけ、当該約定賃料額と当時の近傍同種の建物の賃料相場との関係(賃料相場とのかい離の有無、程度等)、第1審被告の転貸事業における収支予測にかかわる事情(賃料の転貸収入に占める割合の推移の見通しについての当事者の認識等)、第1審原告の敷金及び銀行借入金の返済の予定にかかわる事情等をも十分に考慮すべきである。」
その他の最高裁判例
最高裁平成15年10月21日判決(平成12年(受)第123号)
「借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減額請求権は、賃貸借契約に基づく建物の使用収益が開始された後において、賃料の額が、同項所定の経済事情の変動等により、又は近傍同種の建物の賃料の額に比較して不相当となったときに、将来に向かって賃料額の増減を求めるものと解されるから、賃貸借契約の当事者は、契約に基づく使用収益の開始前に、上記規定に基づいて当初賃料の額の増減を求めることはできないものと解すべきである。」
最高裁平成15年10月23日判決(平成14年(受)第852号)
「本件契約には賃料保証特約が存し、上告人の前記賃料減額請求は、同特約による保証賃料額からの減額を求めるものである。借地借家法32条1項は、強行法規であって、賃料保証特約によってその適用を排除することができないものであるから(最高裁昭和28年(オ)第861号同31年5月15日第三小法廷判決・民集10巻5号496頁、最高裁昭和54年(オ)第593号同56年4月20日第二小法廷判決・民集35巻3号656頁参照)、上告人は、本件契約に賃料保証特約が存することをもって直ちに保証賃料額からの減額請求を否定されることはない。」
最高裁平成16年6月29日判決(平成15年(受)第751号)
「本件各賃貸借契約には、3年ごとに賃料を消費者物価指数の変動等に従って改定するが、消費者物価指数が下降したとしても賃料を減額しない旨の本件特約が存する。しかし、借地借家法11条1項の規定は、強行法規であって、本件特約によってその適用を排除することができないものである(最高裁昭和28年(オ)第861号同31年5月15日第三小法廷判決・民集10巻5号496頁、最高裁昭和54年(オ)第593号同56年4月20日第二小法廷判決・民集35巻3号656頁、最高裁平成14年(受)第689号同15年6月12日第一小法廷判決・民集57巻6号595頁、最高裁平成12年(受)第573号、第574号同15年10月21日第三小法廷判決・民集57巻9号1213頁参照)。したがって、本件各賃貸借契約の当事者は、本件特約が存することにより上記規定に基づく賃料増減額請求権の行使を妨げられるものではないと解すべきである(上記平成15年10月21日第三小法廷判決参照)。」
最高裁平成16年11月8日判決(平成15年(受)第869号)
「借地借家法32条1項の規定は、強行法規と解されるから、賃料自動増額特約によってその適用を排除することができないものである(最高裁昭和28年(オ)第861号同31年5月15日第三小法廷判決・民集10巻5号496頁、最高裁昭和54年(オ)第593号同56年4月20日第二小法廷判決・民集35巻3号656頁、最高裁平成14年(受)第689号同15年6月12日第一小法廷判決・民集57巻6号595頁、最高裁平成12年(受)第573号、第574号同15年10月21日第三小法廷判決・民集57巻9号1213頁参照)。したがって、本件契約の当事者は、本件賃料自動増額条項が存することにより上記規定に基づく賃料増減額請求権の行使を妨げられるものではないから(上記平成15年10月21日第三小法廷判決参照)、上告人は、上記規定により、本件各建物部分の賃料の減額を求めることができるというべきである。」
滝井繁男裁判官の補足意見
1 賃料自動増額特約が存する賃貸借契約においても、賃料減額請求権の行使が認められる場合があり、その際、その当否及びそれが認められた場合の相当賃料額の判断においては、当該契約締結に至る経緯、取り分け本件のような業務委託協定が締結された場合には、その内容及びこれに基づいて締結された契約中の賃料自動増額特約の内容が契約の重要な要素となっているので、衡平の見地に照らし十分に考慮されるべきであることは、多数意見の説示するとおりであると考える。
しかしながら、本件のようなサブリースといわれる契約は、賃貸借契約の中でも特殊なものであり、そこにおける賃料に関する合意は、一般の賃貸借契約におけるとは異なる意味を持っており、その契約において賃料増額特約が存在するにもかかわらず、減額請求が認められる場合に求められる衡平とは何か、その中味をより具体的に明らかにしておくことが重要であると考えるので、その点についての私見を述べておきたい。
2(1)本件のように、賃貸人が、不動産賃貸業を目的とする会社の提案を受け、それに基づいて、金融機関からの多額の融資金によって建物を建築した上で、これを当該提案をした会社に一括して賃貸するという契約を締結した場合、当該賃貸借契約における賃料は、目的物の価格や近傍同種物件の賃料だけでなく、その融資金の返済方法をも念頭において定められることになることが多いのである。
一般に賃貸借契約における賃料は、契約後、目的物の価格の変動や近傍同種物件の賃料の動向によって不相当となることがあることから、借地借家法32条はそのことを理由に賃料の増減を請求しうることを規定しているのである。それに対し、この種サブリースといわれる契約では、賃料は、当該建物の建築資金の返済に充当することが予定されており、その返済額が固定されている以上、契約後の経済事情の変動のみによってその原資となる賃料が容易に減額変更されることはないものとして定められているものと解すべきものである。
このように解すると、建築物を一括して借り受けた賃借人は、これを転貸して、その転賃貸料と賃借料との差額を生じさせることによって利益を得ようとしているのであるから、契約後の経済事情の変動によって、自ら賃貸人となって得ることとなる賃料が減額されても、賃借人として支払う賃料が減額されないのであれば、契約本来の目的を達しないことが起こり得る。しかしながら、そのようなことは、この種契約において目的物を一括して賃借することとした賃借人が一般的に引き受けたリスクと考えるべきものである。
本件契約でも、賃借人となった不動産賃貸業者は、その専門家としての知識と経験を駆使し、当該建築物の賃料収入を予測し、建築工事のために必要となる借入金額とその返済額とを検討した上で、返済額を差し引いた現金収支を明らかにした賃貸事業試算表を作るなどして、賃貸人に本件の事業の採算性を請け合ったというのである。
このように、賃貸人は、専門家としての賃借人による事業収支の予測に基づく提案を受けて、多額の借入金によって建物を建築し、これを賃借人に一括して賃貸することを内容とする業務委託契約と賃貸借契約を締結したものであって、その中で賃料自動増額特約が定められている以上、賃借人が当該建物を転貸することによって受け取る賃料収入がその後の経済事情の変動により減少しても、これにより生ずるリスクは賃借人が引き受けたものとして、これを直ちに賃貸人に転嫁させないというのが衡平にかなうものと考える。この場合、賃借人の提案を受けて賃貸物件を取得したことに伴い発生するリスクは、すべて賃貸人が負担しているのであって、賃借人は、土地の所有や建物建築による経済的リスクを回避する一方で、支払賃料が経済事情の変動によっても減額されないことがあり得るリスクを負担することによって、この種契約における当事者間の衡平は保たれているということができるのである。
(2)他方、本件においては、契約後の経済事情の変動に伴い、賃貸人が本件賃貸物件建築のために借り入れた資金の金利は、契約時の予測を超えて相当程度下落していることがうかがわれる。借入金利は、本件事業収支における算定項目の1つであり、本件契約における賃料額を決する上での重要な要素であったと思われるから、事業資金の借入金利が契約後に下落し、当初金利の変更や借換えなどによって契約時の予測を超えて金利負担が減少したことは、賃料額算定の前提の1つが変更されたことを意味するものであって、それによって生じた利益をひとり賃貸人のみが享受するというのは衡平を欠くというべきである。
このような見地から、本件においては、賃料の減額請求を認めるのが衡平にかなうものと考える。
福田博裁判官の反対意見
1 いわゆるサブリース契約において、賃貸ビル事業者と土地建物提供者との間に賃料自動増額特約が結ばれている場合、それが賃貸借契約の形を採っているときは、借地借家法32条1項の規定が強行法規であるので、同項が適用されるとする考え方には賛成することができない(もちろん、そのような特約を常に有効とすることが可能ではない場合があり得ることは後述のとおりであるが、それは同項の強行法規性によるのではない。)。
2 サブリース契約は、バブル期よりもはるか前の昭和50年代末ころから賃貸ビル事業者によって推進された共同事業方式の一つで、仮にその一部が賃貸借契約の形を採っているとしても、全体の本質は、正に土地の所有者(所有者は、土地の提供にとどまらず、事業内容に見合った建物を建築するのが一般的である。)と賃貸ビル事業者、更には当該建物の建築資金を提供する金融機関や当該建物を設計、施工監理する設計事務所等が合同して行う共同事業にほかならず、事業契約の一部をなす不動産賃貸借契約は、従来から借地借家法が適用されてきたそれとは次元を大きく異にするものである。多数意見の引用する最高裁昭和31年5月15日第三小法廷判決、最高裁昭和56年4月20日第二小法廷判決の事案は、いずれもサブリース契約とは事案を異にするものである。
3 我が国において長年にわたり発展してきた借地借家法は、社会的弱者たる借地人や借家人を保護することに沿革を持ち、ひいてはそれが強行法規性につながっていることは否定できない。他方、時代のニーズに応じて新しく現れたこの種の共同事業方式は、そのような保護を必要としない関係者の間で、関係者の利益追求の思惑が一致して出現したものである。さらに、家賃が右肩上がりの時代にあって、満室保証の下に家賃収入を保証することにより、優良な物件を長期間にわたり一括して借り上げ、社会に提供することも組織的に行われ、現在はその後始末に悩む事業も多々見られる(もとより、いずれの場合であっても、そのような共同事業によって供用される不動産を現実に借り受ける転借人が、借地借家法32条1項の適用を受けて保護されるべきことは、当然である。)。そのような事業にあっては、一部の関係者の見込み違いや過剰な期待などは、ときとして避けることはできないのであって、それらは、基本的には、契約自由、私的自治の原則が支配する分野に属するものである(事業を策定するに当たり、長期にわたる自動増額特約の維持を可能と考えることが、市場経済原理の下で賢明な判断か否かの問題は、法律問題ではない。)。
もし、このような共同事業について、社会経済政策の立場などから、何らかの規制を行うことが必要というのであれば、それは本来立法府のみがよくなし得るところである。また、そのような見込み違いや過剰な期待が、長期的に一部の関係者に過大な負担を与えるときは、倒産法制の活用が避けられないこともあり得よう。なお、昭和50年代後半から昭和60年代初頭にかけては、土地建物信託による共同事業方式が推進された時代もある(これは、信託法制の不備などもあり、結局は主流の方式とはならなかった。)のであって、サブリース契約が建物賃貸借契約の法形式を採っていることを理由に、借地借家法32条1項の適用を認めるというのは、この点からも現実に即したものとはいえない。
4 そのような立法上の手当てもない中において、仮にこのような共同事業契約の内容が著しく現実の事情に合わなくなり、その是正が是非とも必要とされるような場合(例えば天災など)、援用し得る考え方として想定されるのは、例えば、すべての契約に内在する「事情変更の原則」であって、その結果、当事者間の利益配分条項の一部である賃料自動増額特約の有効性の見直しを求められる場合があり得よう。そのような場合には、見直しの対象は、賃料自動増額特約のみならず、当該共同事業に係る他の利益配分に関連する合意等にも及ぶものというべきである。例えば、賃貸ビルの建築資金に係る金融機関の融資条件がサブリース契約の内容と密接にリンクしている場合(賃貸ビル事業者から土地及び賃貸ビル所有者への賃料の支払が、金融機関の指定振込先に対して行われ、ここからの定期的な引落しにより融資金の分割返済が行われる場合など、融資契約が実質的にサブリース契約と不可分一体となっているような場合がこれに当たる。)には、当該融資契約も事情変更の原則により見直されることもあり得よう。
5 これを要するに、借地借家法32条1項は強行法規であるから、共同事業であるサブリース契約(優良不動産物件を確保するための満室保証による一括長期借上げ事業なども含む。)に対しても、当然に適用されるというのは、余りに立法の沿革に沿わぬ考え方といわねばならない。もし、契約の方式が、別の方式、例えば関係者間の組合契約といったもので締結されているのであれば、その適用はないのであろうか。また、例えば満室保証をしたものの、長期間にわたり予定した賃料で借り手がつかない場合は、その適用はどうなるのであろうか。私の考えでは、いずれの契約方式によっても、内在する実質問題は「事業関係者間の利益配分」という同一の問題なのである。
6 このような共同事業は、近年にあっては、長期にわたる賃貸用の不動産物件を相当な規模で社会に供給する役割を果たしてきたのであり、そのような社会のニーズに応える共同事業について、従来の借地借家法の強行法規性を単純に拡張適用するのは、現実的な司法の役割とはいえない。それらは、従来の判例で想定していなかった新しい事業形態なのであり、単純な拡張解釈は、共同事業という新しい事象に無用のひずみと混乱を生じさせる結果を招来する。換言すると、形式的な契約分類によって、借地借家法32条1項を適用することは、いわば強制解合いを共同事業契約の一部についてのみ行うことを可能にするもので、事実上「木を見て森を見ず」の結果をもたらすことにもなりかねないのである。
7 多数意見が引用する最高裁平成15年10月21日第三小法廷判決は、一方においてサブリース契約においても借地借家法32条1項の適用は排除されないとしつつ、他方では賃料減額請求の当否及び相当賃料額の判断に当たっては、関係事情等を十分に考慮すべきであるとしているので、具体的な事案の解決にあっては妥当な結果が導かれるとの考えに立つもののようであるが、同項の強行法規性をよりどころにするのであれば、後段は首尾一貫した論理展開とはいえない。それはそもそも強行法規と呼ぶには適さないものである。一方において強行法規といいながら、賃料自動増額特約の存在を含めた関係事情を十分に考慮するというのは、一般にはなかなか理解しにくい考えといわねばならない。借地借家法32条1項の強行法規性を理由に差戻しを受けた下級審裁判所としては、賃料自動増額特約部分を無効とするだけでは、共同事業者に係る問題を適正に解決できないのであって、共同事業者すべてが納得するような合理的な解決のためには難解な作業を背負い込む可能性がある。
8 以上から、共同事業たるサブリース契約ないし類似の契約の一部が不動産の賃貸借契約の方式によっているからといって借地借家法32条1項が適用されるとすることは妥当でなく、本件において原審が認定した事実関係に照らすと、少なくとも、本件契約における賃料不減額の特約について事情変更の原則を適用すべき事情があるとは認められず、上告人の賃料減額請求権の行使を認めなかった原審の判断は結論において相当であって、本件上告は理由がないものとして棄却すれば足りると考える。
賃料減額についての考え方
サブリース契約について借地借家法32条に基づく賃料減額請求が認められるか否かについては、上記一連の最高裁判例により実務的には決着がついています。
しかし、最高裁判例も「この減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、賃貸借契約の当事者が賃料額決定の要素とした事情その他諸般の事情を総合的に考慮すべきであり、本件契約において賃料額が決定されるに至った経緯や賃料自動増額特約が付されるに至った事情、とりわけ、当該約定賃料額と当時の近傍同種の建物の賃料相場との関係(賃料相場とのかい離の有無、程度等)、第1審被告の転貸事業における収支予測にかかわる事情(賃料の転貸収入に占める割合の推移の見通しについての当事者の認識等)、第1審原告の敷金及び銀行借入金の返済の予定にかかわる事情等をも十分に考慮すべきである。」と述べているとおり、無制限に減額を認めるわけではなく、借地借家法32条の適用を否定する見解と問題意識は共通しているのです。
「結局のところ、サブリース契約において、賃料減額を認めるか否かは、契約締結当時予測していた転貸収入と、現時点における転貸料収入との差額について、賃貸人と賃借人のいずれに、どの程度負担させるかという問題に帰結すると考えられ、これについては、当事者の関係や、サブリース契約締結の経緯等も重要な要素となるから、これらの事情についても十分考慮に入れた上で、判断をすることになろう。」とされているされているところです(「賃料増減請求訴訟をめぐる諸問題(下)」判例タイムズ1290号53頁)。
近時のマンション・アパート建築について
上記サブリース契約に関する賃料減額の問題はバブル崩壊を原因とするものであり、バブル崩壊時特有も問題とも思われてきました。
しかし、近時、相続税対策のため、アパートやマンションを建築する事例が多く見受けられるようになりました。一棟貸し、家賃保証などによるアパート・マンション経営には、このようなリスクがありますので、十分なリスク管理が必要です。
(弁護士 井上元)