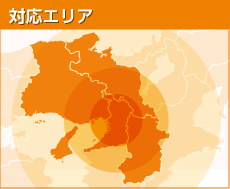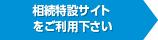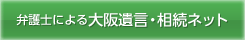説明義務違反の消滅時効に関する最判H23.4.22
契約の一方当事者Yが、契約の締結に先立って、説明義務に違反して契約締結に関する判断に影響を及ぼす情報を提供しなかった場合、相手方Xは、Yの説明義務違反を理由として損害賠償請求を行うことができます。
不動産売買の場合、例えば、対象物件の近隣に暴力団の事務所があるにもかかわらず、YがそれをXに説明しなかったようなケースが考えられます。
この場合のYの責任は、債務不履行責任(契約責任)であるのか不法行為責任であるのか争いがありました。
債務不履行責任(契約責任)であれば消滅時効の期間は民法167条により10年(商事の場合は商法522条により5年)ですが、不法行為責任であれば消滅時効の期間はXが知ってから民法724条により3年(不法行為のときから20年)となります。このように、消滅時効の期間が異なりますので、事案によっては、債務不履行責任(契約責任)であるのか不法行為責任であるのかによって、消滅時効にかかっているか否か結論が変わることになるのです。
この問題につき、最高裁平成23年4月22日判決が判断を下しましたのでご紹介します。
最高裁平成23年4月22日判決
原審
原審は次のとおり判断しました。
(1) 上告人が、実質的な債務超過の状態にあって経営破綻の現実的な危険があることを説明しないまま、被上告人らに対して本件各出資を勧誘したことは、信義則上の説明義務に違反する(以下、上記の説明義務の違反を「本件説明義務違反」という。)。
(2) 本件説明義務違反は、本件各出資契約が締結される前の段階において生じたものではあるが、およそ社会の中から特定の者を選んで契約関係に入ろうとする当事者が、社会の一般人に対する不法行為上の責任よりも一層強度の責任を課されることは、当然の事理というべきであり、当該当事者が契約関係に入った以上は、契約上の信義則は契約締結前の段階まで遡って支配するに至るとみるべきであるから、本件説明義務違反は、不法行為を構成するのみならず、本件各出資契約上の付随義務違反として債務不履行をも構成する。
最高裁判決
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。
なぜなら、上記のように、一方当事者が信義則上の説明義務に違反したために、相手方が本来であれば締結しなかったはずの契約を締結するに至り、損害を被った場合には、後に締結された契約は、上記説明義務の違反によって生じた結果と位置付けられるのであって、上記説明義務をもって上記契約に基づいて生じた義務であるということは、それを契約上の本来的な債務というか付随義務というかにかかわらず、一種の背理であるといわざるを得ないからである。契約締結の準備段階においても、信義則が当事者間の法律関係を規律し、信義則上の義務が発生するからといって、その義務が当然にその後に締結された契約に基づくものであるということにならないことはいうまでもない。
このように解すると、上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものであるから、これには民法724条前段所定の3年の消滅時効が適用されることになるが、上記の消滅時効の制度趣旨や同条前段の起算点の定めに鑑みると、このことにより被害者の権利救済が不当に妨げられることにはならないものというべきである。
コメント
上記最高裁判決は協同組合への出資に際する説明義務違反が問題とされた事案ですが、不動産取引において説明義務違反として争いとなる事案は多く、消滅時効の点に注意が必要です。
(弁護士 井上元)