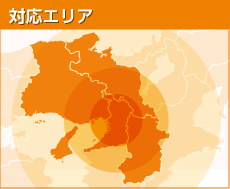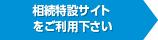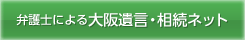敷引特約の有効性に関する最判H23.3.24及び最判H23.7.12
建物賃貸借に際し、賃借人が賃貸人に対し、「敷金」、「保証金」名目で金員を差し入れ、明渡し後、賃貸人は一定額を控除して返還する旨の特約、いわゆる「敷引特約」が規定されていることが多くあります。
この敷引特約が消費者契約法10条により無効となるか否かにつき争われ、最高裁が判断していますのでご紹介します。
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 民法 、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
最高裁平成23年3月24日判決
敷引特約が消費者契約法10条により無効であるか否かについて次のように判示しました。
「(1) まず、消費者契約法10条は、消費者契約の条項が、民法等の法律の公の秩序に関しない規定、すなわち任意規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重するものであることを要件としている。
本件特約は、敷金の性質を有する本件保証金のうち一定額を控除し、これを賃貸人が取得する旨のいわゆる敷引特約であるところ、居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、契約当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、通常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むものというべきである。本件特約についても、本件契約書19条1項に照らせば、このような趣旨を含むことが明らかである。
ところで、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるから、賃借人は、特約のない限り、通常損耗等についての原状回復義務を負わず、その補修費用を負担する義務も負わない。そうすると、賃借人に通常損耗等の補修費用を負担させる趣旨を含む本件特約は、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重するものというべきである。
(2) 次に、消費者契約法10条は、消費者契約の条項が民法1条2項に規定する基本原則、すなわち信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることを要件としている。
賃貸借契約に敷引特約が付され、賃貸人が取得することになる金員(いわゆる敷引金)の額について契約書に明示されている場合には、賃借人は、賃料の額に加え、敷引金の額についても明確に認識した上で契約を締結するのであって、賃借人の負担については明確に合意されている。そして、通常損耗等の補修費用は、賃料にこれを含ませてその回収が図られているのが通常だとしても、これに充てるべき金員を敷引金として授受する旨の合意が成立している場合には、その反面において、上記補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、敷引特約によって賃借人が上記補修費用を二重に負担するということはできない。また、上記補修費用に充てるために賃貸人が取得する金員を具体的な一定の額とすることは、通常損耗等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から、あながち不合理なものとはいえず、敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできない。
もっとも、消費者契約である賃貸借契約においては、賃借人は、通常、自らが賃借する物件に生ずる通常損耗等の補修費用の額については十分な情報を有していない上、賃貸人との交渉によって敷引特約を排除することも困難であることからすると、敷引金の額が敷引特約の趣旨からみて高額に過ぎる場合には、賃貸人と賃借人との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差を背景に、賃借人が一方的に不利益な負担を余儀なくされたものとみるべき場合が多いといえる。
そうすると、消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解するのが相当である。
(3) これを本件についてみると、本件特約は、契約締結から明渡しまでの経過年数に応じて18万円ないし34万円を本件保証金から控除するというものであって、本件敷引金の額が、契約の経過年数や本件建物の場所、専有面積等に照らし、本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額を大きく超えるものとまではいえない。また、本件契約における賃料は月額9万6000円であって、本件敷引金の額は、上記経過年数に応じて上記金額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていることに加えて、上告人は、本件契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、礼金等他の一時金を支払う義務を負っていない。
そうすると、本件敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない。」
最高裁平成23年7月12日判決
同判決は、上記最高裁平成23年3月24日判決と同趣旨の判示をしたうえで、当該事案につき次のように判断しました。
「これを本件についてみると、前記事実関係によれば、本件契約書には、1か月の賃料の額のほかに、被上告人が本件保証金100万円を契約締結時に支払う義務を負うこと、そのうち本件敷引金60万円は本件建物の明渡し後も被上告人に返還されないことが明確に読み取れる条項が置かれていたのであるから、被上告人は、本件契約によって自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上で本件契約の締結に及んだものというべきである。そして、本件契約における賃料は、契約当初は月額17万5000円、更新後は17万円であって、本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっており、高額に過ぎるとはいい難く、本件敷引金の額が、近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して、大幅に高額であることもうかがわれない。
以上の事情を総合考慮すると、本件特約は、信義則に反して被上告人の利益を一方的に害するものということはできず、消費者契約法10条により無効であるということはできない。」
コメント
上記最高裁判決の事案では、月額賃料の3.5倍程度の敷引金は有効とされています。
また、借主が事業者の場合には消費者契約法の適用はありませんので、よほどの暴利でない限り無効とされることはないものと思われます。
(弁護士 井上元)